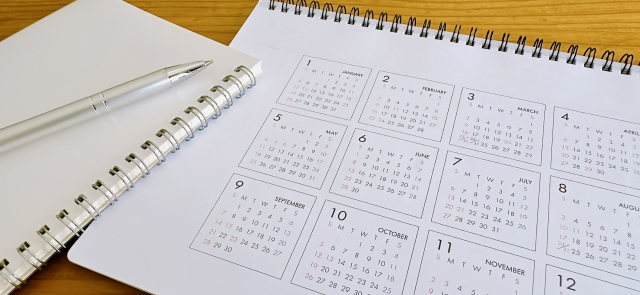厄払いとは?神社とお寺の違い
厄払いとは、厄年に起こりやすいとされる災難や不幸を事前に払い除けるための儀式です。日本では古くから、人生の節目となる年齢に厄が訪れるという考え方があり、その厄を取り除くために神社やお寺で祈願を行う習慣があります。
実は、神社とお寺では呼び方や内容に違いがあります。
- 神社で行われる「厄払い」:すでに身についた厄を取り払う儀式
- お寺で行われる「厄除け」:これから訪れる厄を寄せ付けないようにする儀式
お寺での厄除けは、多くの場合「護摩木」と呼ばれる薪を焚いて行う「護摩祈願」が中心となります。一方、神社での厄払いは、神職によるお祓いが行われます。どちらも目的は同じですが、儀式の内容や雰囲気が異なるため、自分に合った方を選ぶとよいでしょう。
厄払いを受ける時期と年齢
厄年は男女によって異なります。本厄(最も厄の影響が強いとされる年)は以下のように定められています。
- 男性:25歳、42歳、61歳
- 女性:19歳、33歳、37歳、61歳
特に男性の42歳、女性の33歳は「大厄」と呼ばれ、最も注意が必要とされています。また、厄年の前年を「前厄」、翌年を「後厄」と呼び、合わせて3年間は注意が必要な期間とされています。
厄年の数え方は少し複雑で、「数え年」で計算します。数え年とは生まれた年を1歳とし、新年を迎えるごとに1歳を加える数え方です。現代では満年齢が一般的ですが、厄年だけは昔ながらの数え方を使用する場合が多いため注意が必要です。
厄払いを受けるのに最適な時期は、厄年に入る前、または厄年の初めが望ましいとされています。特にお正月の松の内(1月1日~7日)や節分前に受けることが多いようです。これは「予防」という観点からも理にかなっています。
厄払いを受ける前に知っておくべきマナー
服装のマナー
厄払いを受ける際の服装は、神聖な場所にふさわしい清潔感のある落ち着いた装いを心がけましょう。
- 男性:黒や紺の落ち着いたスーツ、または無地のジャケットとスラックスなど
- 女性:スーツ、または落ち着いた色のワンピース、スカートなど
特別かしこまった正装である必要はありませんが、派手な色や露出の多い服装は避けるべきです。また、帽子やコートは社殿に入る前に脱ぎ、ガムや飴なども口に入れないようにしましょう。
具体的に避けるべき服装としては、以下のようなものがあります。
- 過度に華やかな色や柄の服
- 露出が多い服(ミニスカート、深いVネックなど)
- ジーンズなどのカジュアルすぎる服装
- サンダルやビーチサンダル
なお、お寺や神社によっては礼服を指定される場合もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
予約について
厄払いは、多くの場合は当日の申し込みでも対応してもらえますが、神社やお寺の行事と重なる場合や繁忙期には対応できないこともあります。特に年始や節分前は多くの人が厄払いを受けに訪れるため、混雑が予想されます。
確実に厄払いを受けたい場合は、事前に電話などで予約をしておくことをおすすめします。また、神社やお寺によっては事前予約が必須の場合もありますので、公式サイトで確認するか、直接問い合わせるとよいでしょう。
予約の際には、以下の点を確認しておくと安心です。
- 厄払いの所要時間
- 初穂料・祈祷料の相場
- 持ち物や服装の指定
- 当日の流れ
初穂料・祈祷料について
神社での厄払いでは「初穂料」、お寺での厄除けでは「祈祷料」と呼ばれる費用が必要になります。これは神様や仏様へのお供えの意味を持ちます。
初穂料・祈祷料の相場は神社やお寺によって異なりますが、一般的には5,000円から8,000円程度が目安です。ただし、3,000円から数万円まで幅があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
初穂料・祈祷料は、以下のようにして準備します。
- 新札を用意する(汚れや折り目のないものが望ましい)
- 紅白または白の熨斗袋(のし袋)に入れる
- 表書きには「初穂料」「玉串料」「御祈祷料」などと書く
- 裏面には住所と氏名を記入する
なお、「お気持ちで」と言われた場合でも、一般的な相場を目安に包むのがマナーです。受付で両手で丁寧に渡し、お辞儀を添えるとより丁寧です。
厄払い当日の流れとマナー
受付での作法
厄払いの当日は、まず神社やお寺の社務所や受付で手続きを行います。受付では主に以下のような流れになります。
- 受付で必要な書類(名前、住所、生年月日など)に記入
- 初穂料・祈祷料を渡す
- 厄払いの開始時間や場所の案内を受ける
必要情報を記入する際は、丁寧な字で正確に記入しましょう。また、初穂料・祈祷料を渡す際は、両手で袋を持ち、「よろしくお願いいたします」と一言添えるのがマナーです。
受付後は、案内されるまで静かに待ちましょう。この間に心を落ち着かせ、厄払いに備える時間としてください。
手水舎での作法
神社やお寺に到着したら、祈祷を受ける前に手水舎(てみずや)で手と口を清めます。これは身を清めて神聖な場所に入るための大切な作法です。
正しい手水の手順は以下の通りです。
- 右手で柄杓を持ち、左手に水をかけて清める
- 左手で柄杓を持ち、右手を同様に清める
- 再び右手で柄杓を持ち、左手に水を注ぎ、その水で口をすすぐ(直接柄杓から口に水を入れないこと)
- 再び左手を清める
- 柄杓を立てるようにして持ち手部分に水を流して清める
- 柄杓を元の位置に戻し、一礼する
手水の作法は神社やお寺によって若干異なる場合もありますので、現地に掲示されている案内があれば、それに従うとよいでしょう。
祈祷・お祓いを受ける際の作法
案内されたら、指定された場所に座り、神職や僧侶の指示に従って儀式を進めます。一般的な流れとしては以下のようになります。
- 神職や僧侶が来るまで正座をして静かに待つ
- 読経や祝詞を静かに聞く
- お祓いを受ける際は、頭を少し下げる(約15度程度)
- 神職や僧侶と一緒にお辞儀をするよう指示があった場合は従う
なお、正座が難しい方は、事前に神社やお寺に相談しておくとよいでしょう。多くの場合、椅子を用意してもらえることがあります。
お祓いを受ける際のポイントとして、神職や僧侶が祓い串や切麻で皆さんをお祓いする際に頭を少し下げるのがマナーです。神職が皆さまの前を離れたら頭を上げます。
玉串奉りと二拝二拍手一拝の作法
神社での厄払いでは、神職による祝詞奏上の後、玉串奉奠(たまぐしほうてん)と二拝二拍手一拝(にはいにはくしゅいっぱい)の作法が行われることがあります。
玉串奉奠の手順は以下の通りです。
- 神職から玉串を受け取る
- 右手で枝部分、左手で葉部分を持つ
- 神前に進み、玉串を時計回りに180度回して枝が神前に向くようにする
- 玉串を神前に置く
二拝二拍手一拝の作法は以下の通りです。
- 二拝:90度の角度で二回お辞儀をする
- 二拍手:両手を合わせて二回拍手をする
- 一拝:再度90度の角度で一回お辞儀をする
お寺での厄除けの場合は、護摩祈願が終わった後、お護摩札を授与されて終了となることが多いです。指示に従って進めていきましょう。
厄払い後のマナーとお札の取り扱い
厄払いが終わった後も、いくつか気をつけるべきマナーがあります。
まず、授与されたお札やお守りは大切に扱いましょう。お札は神棚や床の間など、清潔で高い位置に祀ります。お守りは身につけたり、常に持ち歩いたりするとよいでしょう。引き出しにしまったままにするのは避けてください。
また、厄払いをしたからといって何でもやってよいわけではありません。厄払いは「心構え」の一つと考え、日常生活でも注意深く行動することが大切です。周囲をよく見て、落ち着いた行動を心がけましょう。
厄払いで授与されたお札やお守りの効力は約1年とされています。翌年、同じ神社やお寺に古いお札やお守りを返納し、新しいものを授与してもらうのが一般的です。
まとめ
厄払いは日本の伝統的な風習であり、厄年に起こりうる災難を事前に払い除けるための大切な儀式です。本記事では、厄払いを受ける際のマナーや作法について解説しました。
要点をまとめると以下のようになります。
- 神社では「厄払い」、お寺では「厄除け」と呼ばれる
- 厄年は男女によって異なり、数え年で計算する
- 服装は清潔感のある落ち着いた装いを心がける
- 初穂料・祈祷料の相場は5,000円程度
- 当日は手水で身を清め、神職や僧侶の指示に従う
- 厄払い後も授与されたお札やお守りを大切に扱う
厄払いの作法やマナーを知っておくことで、初めての方でも安心して厄払いを受けることができます。厄年を迎えた際には、ぜひ本記事を参考に厄払いを検討してみてください。厄払いを通じて、心身ともに清々しい一年を過ごせることを願っています。