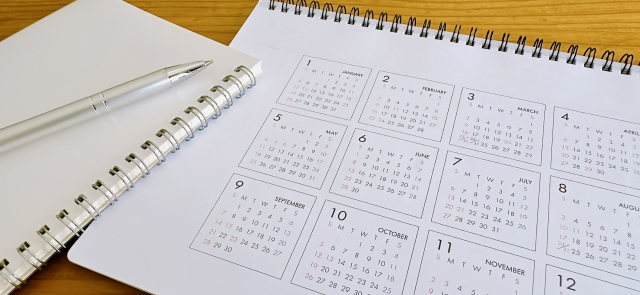厄年とは?その意味と由来
厄年とは、人生の節目にあたる年齢で、災いや不運が起こりやすいとされる年のことです。この考え方は、古代中国や朝鮮半島から伝来し、日本では平安時代から定着しました。例えば、『源氏物語』の「若菜下巻」には、紫の上が37歳の厄年で加持祈願を受けた記述があり、古くから日本人の生活に根付いていることがわかります。
厄年は「本厄」を中心に、その前年を「前厄」、翌年を「後厄」とし、合計3年間続くとされています。特に「本厄」の年は最も注意が必要とされ、健康面や仕事面、人間関係などで思わぬトラブルが起こりやすいと言われています。これは、人間の環境の変化にはおよそ3年かかるという古くからの言い伝えに基づいています。
数え年と満年齢の違い
厄年を知る上で重要なのが「数え年」という考え方です。数え年とは、生まれた時を1歳とし、お正月(1月1日)を迎えるごとに1歳ずつ加える数え方です。これに対して、現代で一般的に使用される「満年齢」は、生まれた日を0歳とし、誕生日ごとに1歳ずつ加えていきます。
数え年で1歳から始まる理由については、胎内で命を宿している期間も年齢として考慮し、命のはじまりを出産前と捉える考え方に基づいています。
簡単な数え年の計算方法は以下の通りです:
- 誕生日前の場合:満年齢 + 2歳 = 数え年
- 誕生日後の場合:満年齢 + 1歳 = 数え年
厄年の早見表は、通常この「数え年」で表記されていることが一般的です。
令和7年(2025年)厄年早見表
令和7年(2025年)に厄年を迎える方は以下の通りです。ご自身やご家族、知人が該当するかどうか確認してみましょう。
男性の厄年
男性の本厄は、数え年で25歳・42歳・61歳が特に重要とされています。特に42歳は「大厄」とされ、最も注意が必要です。
| 前厄(数え年) | 本厄(数え年) | 後厄(数え年) |
|---|---|---|
| 24歳(平成14年生) | 25歳(平成13年生) | 26歳(平成12年生) |
| 41歳(昭和60年生) | 42歳(昭和59年生)※大厄 | 43歳(昭和58年生) |
| 60歳(昭和41年生) | 61歳(昭和40年生) | 62歳(昭和39年生) |
男性の厄年は数え年で80歳(傘寿)まで続くとされ、現代では健康長寿の観点からも高齢の厄除けも重要視されています。
女性の厄年
女性の本厄は、数え年で19歳・33歳・37歳・61歳が特に重要とされています。特に33歳は「大厄」とされ、最も注意が必要です。
| 前厄(数え年) | 本厄(数え年) | 後厄(数え年) |
|---|---|---|
| 18歳(平成20年生) | 19歳(平成19年生) | 20歳(平成18年生) |
| 32歳(平成6年生) | 33歳(平成5年生)※大厄 | 34歳(平成4年生) |
| 36歳(平成2年生) | 37歳(平成元年生) | 38歳(昭和63年生) |
| 60歳(昭和41年生) | 61歳(昭和40年生) | 62歳(昭和39年生) |
女性の厄年も数え年で80歳まで続き、4歳、13歳なども厄年とされていますが、特に上記の年齢は注意が必要とされています。
方位除けとは?
方位除けとは、特定の方角に向かうことが運気に悪影響を及ぼすとされる場合に、その影響を避けるための方法や対策を講じる日本の伝統的な習慣です。引っ越しや旅行、事業の拡大などで新しい方位へ向かう際に、方位除けの考え方を取り入れることで、不運を避け、良い運気を取り入れることを願います。
九星気学と方位の関係
方位除けは九星気学に基づいています。九星気学では、生まれた年によって「本命星」(生まれ星)が決まり、その星が毎年の方位盤上のどの位置にあるかによって、その年の吉凶が決まるとされています。
本命星には以下の9つがあります:
- 一白水星(いっぱくすいせい)
- 二黒土星(じこくどせい)
- 三碧木星(さんぺきもくせい)
- 四緑木星(しろくもくせい)
- 五黄土星(ごおうどせい)
- 六白金星(ろっぱくきんせい)
- 七赤金星(しちせききんせい)
- 八白土星(はっぱくどせい)
- 九紫火星(きゅうしかせい)
方位には「吉方位」と「凶方位」があり、特に引っ越しや大きな決断に関わる移動の際には、どの方角に向かうかを慎重に検討することが大切です。
令和7年(2025年)の凶方位
令和7年(2025年)では、特に以下の凶方位に注意が必要です。
- 八方塞がり(中央):二黒土星 – 最も注意が必要な大凶方位で、八方のすべてが塞がれているため、どの方角に事を起こしてもうまくいかないとされています。
- 表鬼門(東北):五黄土星 – 身辺の変化・変動が多く、怪我や病気に注意が必要です。
- 困難宮(北):七赤金星 – 運気が停滞しやすく、何事にも謙虚な気持ちで取り組むことが大切です。
- 裏鬼門(南西):八白土星 – 表鬼門の正反対に当たる方角で、同様に怪我や病気に注意が必要です。
令和7年(2025年)の恵方(縁起の良い方角)は西南西とされています。
令和7年(2025年)方位除け早見表
令和7年(2025年)に方位除けが必要な方を生まれ年ごとにまとめました。ご自身の生まれ年が該当するかどうか確認してください。
二黒土星(八方塞がり)- 最も注意が必要
以下の年に生まれた方は、令和7年(2025年)に八方塞がりとなります:
- 令和7年生まれ
- 平成28年生まれ
- 平成19年生まれ
- 平成10年生まれ
- 平成元年生まれ
- 昭和55年生まれ
- 昭和46年生まれ
- 昭和37年生まれ
- 昭和28年生まれ
- 昭和19年生まれ
五黄土星(表鬼門)
以下の年に生まれた方は、令和7年(2025年)に表鬼門となります:
- 令和4年生まれ
- 平成25年生まれ
- 平成16年生まれ
- 平成7年生まれ
- 昭和61年生まれ
- 昭和52年生まれ
- 昭和43年生まれ
- 昭和34年生まれ
- 昭和25年生まれ
- 昭和16年生まれ
七赤金星(困難宮)
以下の年に生まれた方は、令和7年(2025年)に困難宮となります:
- 令和2年生まれ
- 平成23年生まれ
- 平成14年生まれ
- 平成5年生まれ
- 昭和59年生まれ
- 昭和50年生まれ
- 昭和41年生まれ
- 昭和32年生まれ
- 昭和23年生まれ
- 昭和14年生まれ
八白土星(裏鬼門)
以下の年に生まれた方は、令和7年(2025年)に裏鬼門となります:
- 令和元年生まれ
- 平成22年生まれ
- 平成13年生まれ
- 平成4年生まれ
- 昭和58年生まれ
- 昭和49年生まれ
- 昭和40年生まれ
- 昭和31年生まれ
- 昭和22年生まれ
- 昭和13年生まれ
厄除け・方位除けの方法
厄年や凶方位の年には、どのような対策を取れば良いのでしょうか。伝統的な方法から現代に合わせた実践方法まで紹介します。
神社やお寺での祈願
最も一般的な厄除け・方位除けの方法は、神社やお寺での祈願です。多くの神社やお寺では、元旦から節分(2月3日)までの期間に厄除け・方位除けの祈願を特に盛んに行っています。
祈願を受けた後は、お札やお守りを授かることが多く、それを身につけたり自宅に飾ったりすることで、厄や凶方位の影響から守られるとされています。方位除けの祈願を行っている神社では、専用の御札やお守りを授かることができます。
近年では、来寺が難しい方のために郵送でのお札授与を行っているお寺も増えています。
中継地を利用した移動
凶方位へ移動しなければならない場合は、直接その方向へ向かうのではなく、吉方位の場所を経由(中継地として利用)することで、凶方位の影響を和らげる方法もあります。たとえば引っ越しの際には、一度吉方位の場所に立ち寄ってから目的地に向かうことで、方位除けの効果を期待します。
日常生活での心がけ
厄年や凶方位の年には、日常生活でも以下のような点に心がけるとよいでしょう:
- 健康管理に特に気を配る
- 無理な予定を詰め込まない
- 新しいことへの挑戦は慎重に
- 人間関係を大切にする
- 金銭管理に注意する
厄年中は特に健康面で注意が必要とされ、凶方位の方角への引っ越しや旅行、出張などは可能であれば避けるか、事前に方位除けの祈願を受けておくことが望ましいとされています。
まとめ:厄年・凶方位を前向きに過ごすために
厄年や凶方位の年は確かに伝統的に注意が必要な時期とされていますが、必要以上に恐れる必要はありません。適切な厄除け・方位除けの祈願を受け、日常生活で無理をせず、前向きな気持ちで過ごすことが大切です。
令和7年(2025年)に厄年や凶方位に該当する方は、年明けから節分までの期間に、お近くの神社やお寺で厄除け・方位除けの祈願を受けることをおすすめします。もしも厄年が過ぎてしまっていた場合でも、「厄年を無事に過ごせたことへの感謝」の気持ちを込めてお礼参りをするのも良いでしょう。
方位除けについても、凶方位を避けられない場合は事前に祈願を受け、中継地を利用するなどの工夫をすることで、より安心して行動することができます。
日本の伝統文化である厄除けや方位除けの習慣を通じて、私たちの先人の知恵に触れることもまた、意義のあることではないでしょうか。令和7年(2025年)が皆様にとって実り多き一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。