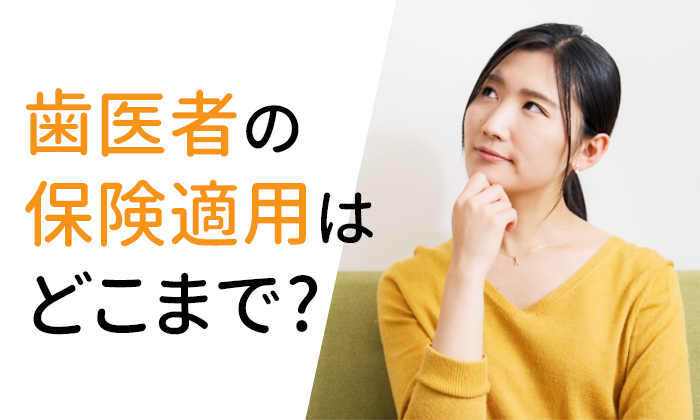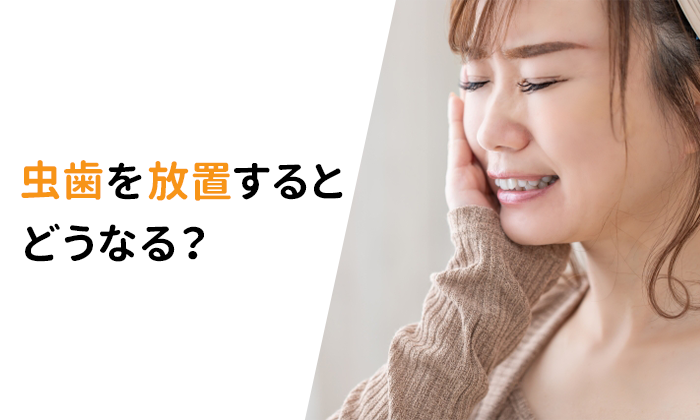歯科治療における保険適用の基本原則
歯科治療で保険が適用されるのは「機能回復のための最低限の治療」という基本原則があります。つまり、歯の基本的な機能を回復させるために必要な治療は保険診療の対象となりますが、見た目の改善や快適性を重視した治療は自費診療となる場合が多いのです。
保険診療では、患者さんの費用負担は1〜3割となり、残りは国や自治体が負担します。一方、自費診療では治療費の全額が患者さんの負担となるため、同じ治療でも費用に大きな差が生じることがあります。
保険適用の判断基準
保険適用の判断は以下の基準に基づいて決められます:
- 歯の機能回復が主な目的であること
- 医学的な必要性が認められること
- 厚生労働省に認可された材料・方法を使用すること
- 治療内容が保険診療のルールに適合していること
混合診療の原則禁止
原則として、保険診療と自費診療を同時に受けることはできません。例えば、虫歯治療の一部だけを保険で行い、残りを自費で行うことは認められていません。ただし、「保険外併用療養費制度」の対象となる治療については、保険診療との併用が可能です。
保険適用される具体的な治療内容
歯科治療の中で保険が適用される主な治療内容を詳しく見ていきましょう。
基本的な治療
虫歯治療、歯周病治療、根管治療、抜歯などの基本的な治療は保険適用となります。これらの治療は歯の機能回復を目的とした必要最低限の治療として位置づけられています。
具体的には以下のような治療が保険適用されます:
- 虫歯の除去と充填治療
- 歯周病の治療(歯石除去、歯周基本治療など)
- 歯の神経の治療(根管治療)
- 親知らずなどの抜歯
- 歯のクリーニング(治療目的の場合)
詰め物・被せ物
詰め物や被せ物についても、保険適用となる材料と適用外の材料があります。
保険適用される材料:
- コンポジットレジン(プラスチック製の白い詰め物)
- 金銀パラジウム合金(いわゆる銀歯)
- 硬質レジン前装冠(前歯の白い被せ物)
- CAD/CAM冠(条件付きで白い被せ物)
CAD/CAM冠は、4番目・5番目の歯が保険適用となります。6番目の歯については、7番目の歯が上下左右4本すべて残っている場合に保険適用となります。また、金属アレルギーの方は、医師の診断書があれば4番目・5番目・6番目・7番目の歯が保険適用となります。
入れ歯・ブリッジ
歯を失った場合の治療では、プラスチック製の入れ歯やブリッジが保険適用となります。全体がプラスチック素材でできている入れ歯や、金銀パラジウム合金を使用したブリッジは保険診療で受けることができます。
ただし、金属床義歯やノンクラスプデンチャーなど、審美性や機能性を重視した入れ歯は自費診療となります。
予防歯科・定期検診
2020年4月の診療報酬改定により、予防歯科の一部が保険適用となりました。口腔内に虫歯や歯周病などの疾患が認められる場合、重症化を防ぐための予防治療に保険が適用されます。
定期検診については、保険適用で受けることができ、3割負担の場合は約3,000円程度が費用の目安となります。ただし、完全に健康な状態での予防処置は自費診療となることがあります。
保険適用外となる治療
歯科治療の中で保険適用外となる主な治療について説明します。
審美治療
見た目の美しさを重視した治療は、原則として保険適用外となります。具体的には以下のような治療が該当します:
- ホワイトニング(歯の漂白)
- セラミックの詰め物・被せ物
- ジルコニアの被せ物
- 審美目的の矯正治療
- ラミネートベニア
これらの治療は、機能回復を目的とした最低限の治療という保険診療の基準を超えるため、自費診療となります。
インプラント治療
インプラント治療は、保険適用されません。1本単位で費用が発生し、一般的な費用相場は1本あたり30万円〜40万円となります。高額な治療費がかかりますが、機能性や審美性の面で選択肢の一つとなります。
矯正治療
矯正治療は、基本的に審美目的と判断されるため保険適用外です。小児矯正の場合は30万円〜50万円、成人矯正の場合は60万円〜150万円程度の費用がかかります。
ただし、顎変形症として診断された場合の外科矯正治療は保険適用となることがあります。この場合、指定された医療機関での治療が必要となります。
保険診療の制限とルール
保険診療には様々な制限とルールがあります。
治療回数の制限
保険診療では「1回の治療につき、この範囲まで」というルールがあり、1日でできる処置の量や範囲が定められています。そのため、一度に複数の治療を行うことができず、何度も通院する必要があります。
この制限は、多くの患者さんに平等に医療を提供するための仕組みですが、患者さんにとっては通院回数が増える要因となります。
使用できる材料の制限
保険診療では、使用できる材料や技術が厳格に制限されています。最新の治療法や高性能な材料を使用することができないため、治療の選択肢が限られることがあります。また、治療にかけられる時間にも制限があるため、時間をかけた丁寧な治療が難しい場合もあります。
まとめ
歯科治療における保険適用は、「機能回復のための最低限の治療」という基本原則に基づいています。虫歯治療、歯周病治療、基本的な詰め物・被せ物、入れ歯・ブリッジなどは保険適用となりますが、審美性や快適性を重視した治療は自費診療となることが多いです。
保険診療には様々な制限があるものの、基本的な歯の機能を回復させるには十分な治療が可能です。一方で、より高い審美性や機能性を求める場合は、自費診療を検討する必要があります。治療を受ける際は、歯科医師と十分に相談し、自分の希望と予算に合わせた適切な治療選択を行うことが重要です。
また、高額療養費制度や医療費控除などの制度を活用することで、費用負担を軽減できる場合もあります。定期検診や予防歯科を活用して、大きな治療が必要になる前に予防することが、健康面でも経済面でも有効な方法といえるでしょう。