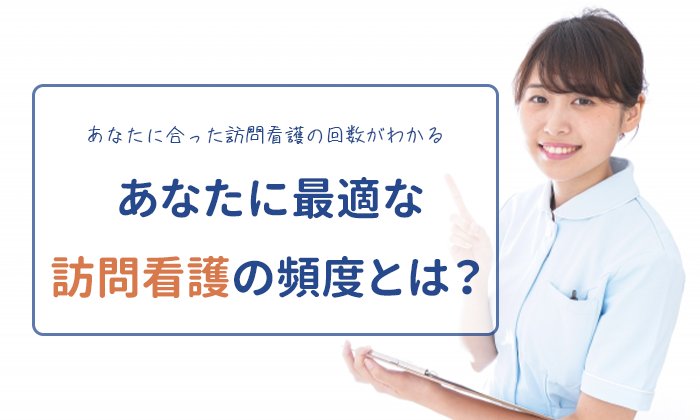医療保険と介護保険の基本的な違い
訪問看護では、原則として「医療保険」と「介護保険」を同時に利用することはできません。要支援・要介護認定を受けている場合は介護保険が優先されますが、特定の疾病や条件によっては医療保険が適用されるケースもあります。
- 医療保険は主に治療や症状管理を目的としたサービス
- 介護保険は日常生活の支援や介護予防を目的としたサービス
対象者の違い
医療保険の対象者:
- 40歳未満で主治医から訪問看護指示書が交付された方
- 40歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方
- 要支援・要介護認定を受けていても、厚生労働大臣が定める疾病(別表7)に該当する方
介護保険の対象者:
- 65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方
- 40歳以上65歳未満で特定疾病(16種類)が原因で要支援・要介護認定を受けている方
利用上限と制限の違い
医療保険:
原則1日1回、週3回までの利用となります。ただし、厚生労働大臣が定める疾病や特別訪問看護指示書がある場合は、週4回以上の利用も可能です。
介護保険:
利用回数に制限はありませんが、要介護度に応じた支給限度額の範囲内での利用となります。
自己負担額の違い
医療保険と介護保険では、自己負担額の計算方法や上限が異なります。どちらの保険を利用するかによって、月々の負担額が変わるため注意が必要です。
医療保険での自己負担
- 未就学児:2割負担
- 義務教育就学児〜69歳:3割負担
- 70歳以上:原則1割(現役並み所得者は3割)
- 75歳以上:原則1割(現役並み所得者は3割)
医療保険には月間の支給限度額がありません。高額療養費制度も利用可能です。
介護保険での自己負担
- 所得に応じて1割・2割・3割のいずれか
- 支給限度額を超えた分は全額自己負担
- 要介護度が高いほど支給限度額も高くなります
特定疾病と保険適用の関係
訪問看護の保険適用においては、特定疾病の有無が重要な判断ポイントとなります。特に40歳以上65歳未満の場合、16の特定疾病への該当有無で介護保険利用の可否が決まります。
介護保険の16特定疾病
- がん(末期がん)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症(MSA)
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
医療保険優先となるケース
- 要介護認定を受けていても、厚生労働大臣が定める疾病(別表7)に該当する場合は医療保険が優先されます
- 高度な医療的ケアが必要な場合は医療保険での訪問看護が適用されます
利用申し込みの流れ
訪問看護の利用申し込み方法は、医療保険と介護保険で異なります。いずれも主治医の「訪問看護指示書」が必要となります。
医療保険での申し込み手順
- かかりつけ医(主治医)に相談
- 医師による「訪問看護指示書」の発行
- 訪問看護ステーションの選定と利用契約
- 訪問看護の開始
介護保険での申し込み手順
- 要介護認定の申請
- 認定調査の実施
- 要介護度の認定
- ケアマネジャーによるケアプラン作成
- 医師による「訪問看護指示書」の発行
- 訪問看護ステーションの選定と利用契約
- 訪問看護の開始
経済的負担を軽減する制度
訪問看護の利用にあたっては、経済的負担を軽減するための公的制度も活用できます。特に医療保険利用時は高額療養費制度が有効です。
高額療養費制度
医療保険での訪問看護利用時、1ヶ月の医療費自己負担額が一定額を超えた場合、高額療養費制度が適用されます。年齢や所得によって上限額が異なりますが、経済的な負担を大きく軽減できます。
自費での訪問看護
- 保険適用外のサービスも自費で利用可能
- 公的保険の制限を受けないため、柔軟なサービス提供が可能
- 保険と自費サービスの併用も可能
まとめ
訪問看護における医療保険と介護保険の違いは、対象者、利用上限、自己負担、申し込み方法など多岐にわたります。
ご自身やご家族の状況に合わせて最適な制度を選択し、必要に応じて医師やケアマネジャーに相談されることをお勧めします。公的制度や自費サービスも上手に活用し、安心して訪問看護を利用できる環境を整えることが大切です。