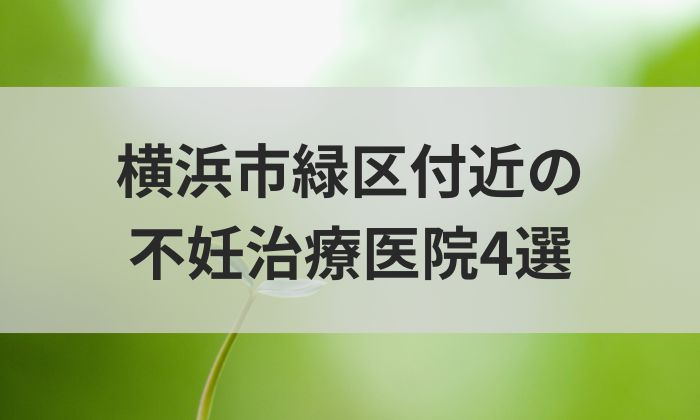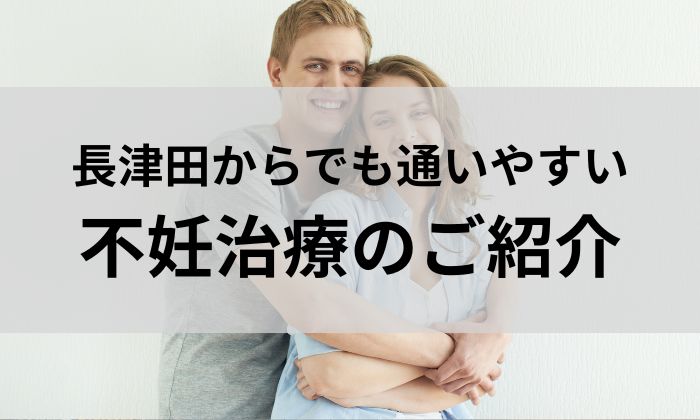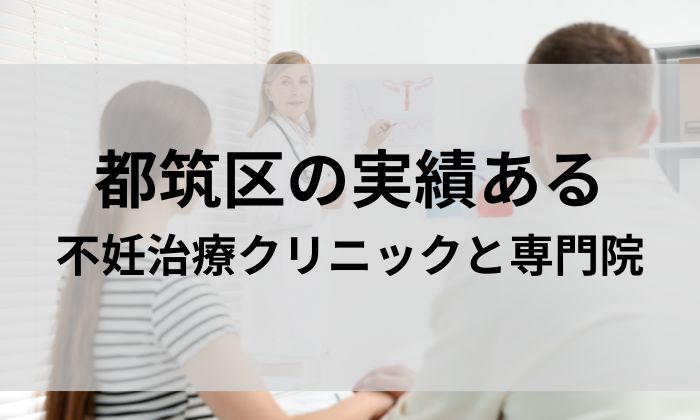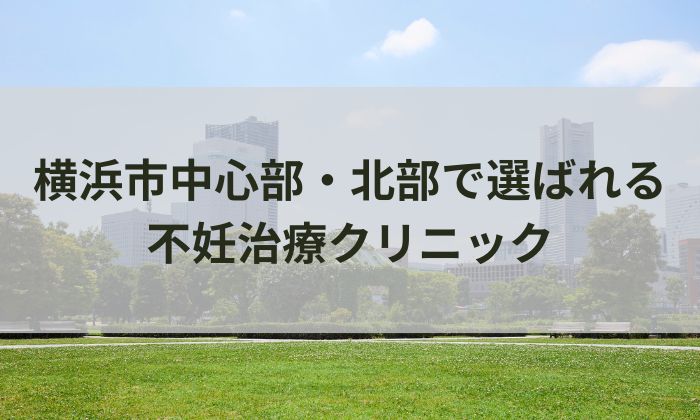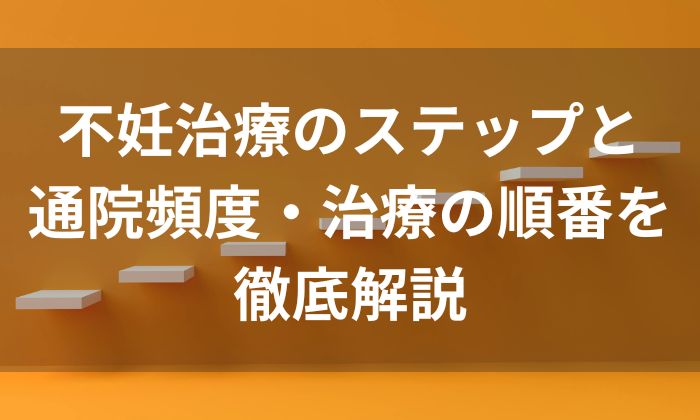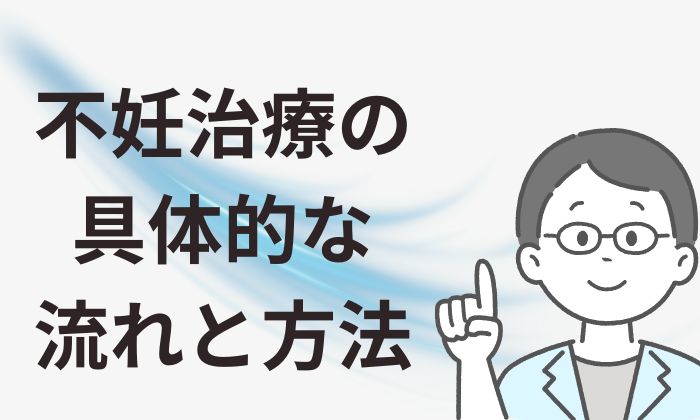生殖医療ガイドラインとは
生殖医療ガイドラインは、不妊症治療の標準となる検査・治療方法や推奨される時期、適応基準を整理した指針です。2025年最新版では、保険適用範囲の拡大、高齢不妊治療のリスク管理、非配偶者間生殖補助医療基準の強化など幅広く改訂されました。
保険適用と助成制度
近年の改訂で、体外受精や顕微授精も保険適用となり、治療費の負担が軽減されています。治療開始時の女性年齢が43歳未満であること、体外受精は通算6回、40歳以上43歳未満は3回までの回数制限が設けられています。高額療養費制度や自治体ごとの助成金制度も併用可能です。
一般的な治療方法の種類と基準
ガイドラインで推奨される治療法は以下のとおりです。まず「タイミング法」(自然妊娠を目指す周期管理)、次に「人工授精」、さらに「体外受精(IVF)」や「顕微授精(ICSI)」といった生殖補助医療へと段階的に移行します。各治療法は医学的根拠・適応基準が定められています。
治療法の選択基準とリスク管理
ガイドラインでは、治療の選択は年齢や医学的状態による適応基準をもとに決定されます。高齢妊娠や流産歴・男性不妊など状況別のプロトコルも整備されており、リスク説明やインフォームド・コンセントの徹底が義務づけられています。副作用リスクや複数回施行時の管理も重要です。
ガイドライン遵守のメリットと注意点
公式ガイドラインをもとにした治療は、エビデンスに基づく安全性と公平性が担保されます。治療前には必ず十分な説明を受け、自分の状況に合った選択をすることが重要です。治療効果は個人差があるので、過度な期待や誇大表現には注意して、納得できる治療プロセスを選びましょう。