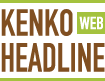新型コロナウイルス対策に奔走する公益社団法人東京都医師会に対し、LDH JAPANが支援活動の一貫としてコーヒーバッグを無償で提供したことが分かった。LDH JAPANから送られた支援物資はオリジナルコーヒーバッグ5000袋・マグカップ・ポットなど。都道府県別感染者数が全国最多となる東京都では、医療現場のひっ迫を回避することが喫緊の課題。そうした最前線で働く医療従事者に向けてひと時の憩いを贈った形となる。
ニュースカテゴリーの記事一覧
外出自粛で気になる子どもの健康管理、最も気をつけていることは「手洗い」
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、「緊急事態宣言」の対象地域が全国に拡大された。不用不急の外出自粛により自宅で過ごす時間が増加し、家庭内感染と見られる事例も増えているが、各家庭での健康管理はどうなっているのだろうか? 予防医学を取り入れたエイジングケア商品で知られるアンファーが、全国4700人を対象に「子どもの健康管理」をテーマにインターネット調査を実施、最も気をつけていることは「手洗い」という実態が明らかになった。
新型コロナウイルス「PCRセンター」設置へ 東京都医師会が発表
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、公益社団法人東京都医師会は17日に緊急記者会見を開き、都内の地区医師会と連携してPCR検査を受診できる「PCRセンター」を新たに設置する意向を発表した。
WEB会議にも有効な「増えみせ」スタイリング剤どう使う?プロに聞いた
新しい出会いが増える春。しかし「緊急事態宣言」の対象7都府県はオフィス出勤者の最低7割減を要請されるなど、企業のテレワーク化が進んでいる。初対面の人とWEB会議をする機会も多い中、編集部では髪が増えて見える!?スタイリング剤の話題をキャッチ。その効果と自宅でできるスタイリング技を美容のプロに聞いた。
話題となっているのは、スカルプシャンプーで知られる「スカルプD」から新たに登場したスタイリングシリーズ。各アイテムに黒い色素や一部商品には炭の成分が配合されており、頭皮が透けにくく、ボリューム感を出しながら手軽にスタイリングできるのが特徴だという。東京・新宿「√5 SHINJUKU」の水戸佑歩さんに使い方のコツを聞くと「サロンの仕上がりに近づけるためにおすすめなのはライン使い」とのこと。
まず、モデル役の男性に一度シャンプーしてもらい、ドライヤーで7〜8割まで乾かしたところで、「ボリュームキープミスト」をスプレー。「濡れている髪に使うよりも、ちょっと乾かしてからスプレーして、もう一度乾かしながらセットするとボリュームが出やすいですね」と水戸さん。
本の目利きがおすすめ「新生活を迎える人に読んでほしい本」【しんどい時に読みたい3冊】
まもなく迎える新生活。新しい勉強や仕事、生活が楽しみという人もいれば、慣れない人間関係や職場、環境に移ってしばらくは戸惑うことも……。毎日たくさんの人や本と接するプロの書店員さんに、新生活を迎える人に寄り添ってくれるようなおすすめ本を選んでもらった。ぜひお近くの街の本屋さんで探してみては?
新生活を迎える人に読んでほしい! 本の目利きがおすすめする、弱い自分を認められる本
もうすぐ新生活!気分が上向くヒント集
まもなく迎える新生活。新しい勉強や仕事、生活が楽しみという人もいれば、慣れない人間関係や職場、環境に移ってしばらくは戸惑うことも……。毎日たくさんの人や本と接するプロの書店員さんに、新生活を迎える人に寄り添ってくれるようなおすすめ本を選んでもらった。ぜひお近くの街の本屋さんで探してみては?
新型コロナで「医療的緊急事態宣言」東京都医師会、国に先駆け
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府が7日に「緊急事態宣言」を発出することを表明した。これに先立って公益社団法人東京都医師会は6日、千代田区の東京都医師会館にて緊急記者会見を行い、「医療的緊急事態宣言」を発出した。
STOP新型コロナ!東京都医師会「ここから2週間が本当に勝負」
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。東京都では3日、新たな感染者数を89人と発表、感染経路が分かっていない人は55人、都内で感染が確認されたのは3日現在であわせて773人となった。今週末も不要不急の外出自粛が呼びかけられる中、改めて新型コロナウイルス対策について、公益社団法人東京都医師会副会長の角田徹さんに話を聞いた。
新型コロナ対策で気になる「オンライン診療」とは?
全世界で猛威を振るう新型コロナウイルスに対し、厚生労働省が「オンライン診療」の促進に乗り出している。医療機関での感染リスクを回避できるとして、注目を集める「オンライン診療」だが、実際にどのような流れで受診すれば良いのだろうか。オンライン診療サービス「スマホ診」を中心に診療を行う中央区の「つなぐクリニックTOKYO」で話を聞いた。
新生活に疲れたら……上手に「気分転換」グッズ【気分が上向くヒント集】
新生活に合わせて、身の回りの文房具や家具などをお気に入りのものに新調する人も多いだろう。これから新生活を迎える人に、生活雑貨専門店「ロフト」広報部おすすめの気分転換グッズをご紹介。慣れない環境に緊張して疲れやストレスが溜まったら、早めに帰って自宅でゆっくりケアしよう。
『スタンフォード式 最高の睡眠』西野教授が語る「睡眠のメカニズム」
新生活のスタートでより良い睡眠を取るにはどうしたらいいか、ベストセラー『スタンフォード式 最高の睡眠』著者で米スタンフォード大学医学部精神科教授、株式会社ブレインスリープ代表取締役の西野精治先生に「日本人の睡眠」について聞くシリーズ。後篇では西野教授に詳しい「睡眠のメカニズム」について聞き、そこから「睡眠の質」を改善するポイントを探る。