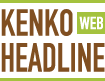政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の会長を務めた尾身茂氏が「第9波の入り口に入ったのではないか」と発言して注目を集めている。東京都医師会の猪口正孝副会長は、定例記者会見で都の感染動向について次のように語った。
ニュースカテゴリーの記事一覧
都医師会・尾﨑会長、少子化対策の財源に私見「全世代平等な負担となるのが望ましい」
東京都医師会の尾崎治夫会長は、13日の定例記者会見の中で政府が推進するオンライン資格確認や少子化対策の財源について意見を述べた。
都医師会・尾﨑会長、超高齢化社会に警鐘「2025年以降受診できない患者さんが増えてくる」
新型コロナウイルスが5類に移行して約1カ月。東京都医師会は13日、都内で今後の医療課題について定例記者会見を行った。
管理栄養士が語る「耳年齢」維持のカギ。食事の時間を決めて「青魚と青菜」で血管と神経の若さを意識
「味覚に与える音の影響」について解説
世界トップクラスのシェアを持つデンマークの補聴器メーカーの日本法人GNヒアリングジャパン株式会社が6月6日、都内でポストコロナで変化している補聴器のニーズや難聴ケアの重要性などについて発表した。
発表会には管理栄養士で医学博士の本多京子氏が登壇し「母の介護で気づく老いの準備『耳年齢』を意識した健康的な暮らし方」というテーマで講演を行った。
本多氏は管理栄養士という立場から「食べ物を美味しく味わうことは幸せの基本。美味しさを感じるにはまずは味覚というものがあると思うが、それだけではない。例えば肉を焼いている時のジュージュー、せんべいを食べている時のバリバリ、レタスを食べている時のシャキシャキ、揚げたてのフライを食べた時に口の中でする衣のザクザクという音や感覚に“ああ、揚げたてっておいしいな”と思うように音も美味しさの大切な条件なのではないかと思う」と語った。
そして、優雅な音楽、インドの雑踏の音、無音という3つの音の中でそれぞれ紅茶を飲むという実験を行い「音の環境によっても同じものを味わっても味わいが違うような気がする。美味しさには味だけではなくいろいろな要素が影響している。もし音がキャッチできなくなれば、食事の美味しさも半減するのではと思う。ただの水も色の違うコップで飲むと、視覚により味が変わって感じられる。私は日体大で教えていたんですが、授業の中で液体の色が見えないようにして鼻をつまんでリンゴジュースと桃のジュースを飲んでもらうと学生は飲み分けができなかった。香りや色がないと何ジュースか分からない。つまり私たちが物を食べ、幸せを感じる時には味だけではなく、いろいろな要素が影響している。もし音がキャッチできなくなれば、食事の美味しさも半減するのではと思う」などとかつての実験の結果もまじえながら「味覚に与える音の影響」について解説した。
あなたの「耳の聞こえ」は大丈夫? コロナ禍で難聴発見が遅れるケースも
6月6日は補聴器の日
「あなたの耳の聞こえは大丈夫ですか?」と聞かれたら大概の人は「大丈夫」と答えるだろう。では「コロナ前と比べては?」と聞かれるとどうだろう。そして高齢となった父母は?「補聴器の日」の6月6日に「聞こえ」について考えてみるのもいいのでは?
世界トップクラスのシェアを持つデンマークの補聴器メーカーの日本法人GNヒアリングジャパン株式会社はこの日、発表会を行い「ポストコロナ難聴増加の背景にある発見の遅れについて」というテーマで同社のマーケティング部プロダクトマネジャーの大久保淳氏がスピーチを行った。
大久保氏によると日本と海外の難聴者率には大きな違いはないものの補聴器の所有率は日本は圧倒的に少ないという。ただし難聴に気づいてから補聴器を保有するまでの期間が2018年の調査では6年以上だったものが2022年では2~3年に短縮。
多くの企業が取り組む「健康経営」キーワードは“従業員が主役”
なぜ今、多くの企業が「健康経営」に取り組むのか?
2023年4月、健康保険組合連合会が公表した情報によると、主に大企業の会社員らが加入する健康保険組合の8割で2023年度の収支が赤字の見通しとなったことがわかった。高齢化の進展によって高齢者の医療費を賄うための拠出金が増えることなどから、赤字額が前の年度のおよそ2倍に膨らむ見通しだ。高齢者医療への拠出金は、いわゆる『団塊の世代』が75歳以上となる2025年にかけてさらに増えていく見込みだ。企業において「健康経営」が企業損益に直結する“経営課題”になっているのだ。
企業が「健康経営」に取り組む理由は企業が負担する医療費の削減だけではない。企業のイメージが高まることや、人材の確保、労働生産性の向上&リスク管理、従業員の離職率低下など様々なメリットがある。
健康経営と言えば、従来は健康診断受診率やストレスチェック受検率など、企業の実践度が中心とされてきたが、HR総研の「健康経営」に関するアンケート調査(調査期間2019年11月29日~12月6日)によると、健康経営施策に積極的に取り組むのは疾病のハイリスク層となりやすい「健康意識が低い人」ではなく、「普段から健康意識の高い人」が約6割を占め、なかなか実践効果に繋がりにくい取り組み状況であるとされている。さらに、新たな取り組みやサービスを取り入れても、従業員がやる気にならない、続かないというのが企業の悩みだ。
5類移行後の “血液不足” を解消へ 東京都医師会が都内で「献血会」を開催
新型コロナウイルスの5類移行を受け、感染状況がひと段落した一方で、若者を中心に献血者数が減少傾向にあるという。そこで東京都医師会は12日、医師会内部や近隣ビルのテナント企業、事業者などに呼びかけ、都内で献血会を開催した。
5類移行後、新型コロナにかかったら?医療機関受診のポイントを東京都医師会が解説
東京都医師会は9日、5類移行後の課題と対策について定例記者会見を行い、5類移行後の医療機関受診のポイントを解説した。
5類移行後の新規陽性者数は?東京都医師会、今後のモニタリング分析について説明
東京都医師会は9日、5類移行後の課題と対策について定例記者会見を行い、東京都のモニタリング項目の分析・総括について説明した。
都医師会・尾﨑会長、5類移行で会見「決してコロナがなくなったわけではない」
新型コロナウイルスの感染症法の位置付けが8日付で5類に移行したことを受け、東京都医師会は9日、5類移行後の課題と対策について定例記者会見を行った。
線虫がん検査のHIROTSUバイオサイエンス広津代表らが福岡県知事を表敬訪問
線虫がん検査の開発・販売を行うHIROTSUバイオサイエンスの広津崇亮代表らが11日、福岡県の服部誠太郎知事を表敬訪問。愛犬用の線虫がん検査 「N-NOSE わんちゃん」の本格実用化や、この検査が福岡県で行われている人と動物の健康と環境の健全性を守る取り組み「ワンヘルス」に貢献するものであることなどを報告した。
表敬訪問では、広津代表が、バイオベンチャーの創出などを目的とした「福岡バイオバレープロジェクト」における支援の御礼や、「N-NOSE」の実用化の歩みから「N-NOSE わんちゃん」を始めとした事業の現状について服部知事に報告した。また、同席した児玉どうぶつ病院の児玉和仁院長は共同研究のきっかけや検査の意義について説明した。
アジア獣医師会連合会長で公益財団法人日本獣医師会の藏内勇夫会長は「コンパニオンアニマルとして人生の伴侶として生きている犬のがんが多発しているなか、“N-NOSE わんちゃん”のような新しい技術ができることはありがたいこと。福岡バイオバレープロジェクトで支援したバイオスタートアップ企業がユニコーン企業になり、またダボス会議に招待されたことは感無量です。“ワンヘルス”の取組みが大きく前進しているなか、これからも旗振り役としてご協力をお願いします」とコメント。
服部知事は「ユニコーン企業に成長しダボス会議に呼ばれ、グローバルに事業を展開されおめでとうございます。昨年の早期すい臓がん検査の事業化、そして愛犬を対象とした“N-NOSE わんちゃん”と着実に実績を上げていることは大変喜ばしいです。福岡バイオバレープロジェクトを推進する立場として、当プロジェクトに参加している200社を超える後輩企業にもご支援ご指導をお願いしたいです。県は今後も“ワンヘルス”を推進していくので引き続きよろしくお願いします」と挨拶した。